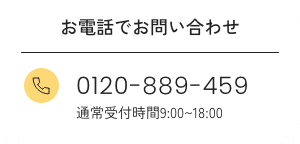建設業が強くなる節税とお金の関係は?

投稿者プロフィール

-
中小企業社長専門の経営コンサルタント兼税理士。
1977年生まれ、札幌出身。大手税理士事務所在籍中、税理士試験に合格。「試算表を作るだけ」の業務が中心で、経営支援に踏み込めない現状に強いジレンマを抱える。大手事務所を退所し、コンサル型の税理士事務所に入所するも思い描く支援とのギャップに苦悩。28歳の頃にお客さんゼロ・計画なしという状態で独立を決意。自分自身が事務所経営に苦しんだ経験から「経営者は孤独で、悩んでも税理士に相談しにくい」という現実を身をもって痛感。ふとしたきっかけで参加した勉強会で「税理士=税金や会計処理だけではない。経営戦略まで踏み込んでサポートできる存在でありたい」という想いを強くする。様々な経験を経て、現在は北海道札幌市白石区で「建設業や動物病院をはじめ、多業種の経営者を「数字」と「現場」の両面で支えている。単価・売上・利益向上と財務、人事・採用マーケティングのサポートを得意とする経営コンサルタント。
最新の投稿
 経営のお話し2025年5月18日スケールアップの壁を超える!売上2億円超えの経営者がやっている行動5選
経営のお話し2025年5月18日スケールアップの壁を超える!売上2億円超えの経営者がやっている行動5選 経営のお話し2025年5月6日年収1000万円以上の経営者必見!年収1億円超の会社との決定的違いとは
経営のお話し2025年5月6日年収1000万円以上の経営者必見!年収1億円超の会社との決定的違いとは 経営のお話し2025年5月5日このままでは会社が危ない!コスト高騰時代を生き抜く利益改革の最前線
経営のお話し2025年5月5日このままでは会社が危ない!コスト高騰時代を生き抜く利益改革の最前線 建設業2025年4月29日建設業の経営者と税理士の間違った関係
建設業2025年4月29日建設業の経営者と税理士の間違った関係
札幌市白石区の建設業の経営に強い千葉税理士事務所です。
起業すると「節税」という言葉をよく耳にするようになります。
先輩経営者も「節税したほうがいい」ということを話してくるケースも多いものです。
でも、間違っている情報も多いので気を付けましょう。
(目次)
1.建設業によくある節税TOP3とは
2.建設業の経営者によって節税に関する答えが違う理由
3.建設業のための節税とお金の関係をよくする方法
4.まとめ
1.建設業によくある節税TOP3とは
建設業の経営者同士で話をするときに節税が話題になることが良くあります。
私たちもお客様から節税の相談をされるケースが良くあります。
昔は節税を中心に話をしており、それを経営アドバイスと思っていました。
その経験から建設業によくある節税についてお話しさせていただきます。
①倒産防止共済節税
倒産防止共済は掛金が損金(必要経費)になるというものです。
本来は取引先が倒産した時に掛金の10倍の借入ができるというものですが、税務署側の見方も金融商品としての性質で見ているのが実態です。
一般的には高額な支払いをしても一発経費になることはほとんどないので、魅力的な節税商品としてよく使われます。
令和6年10月より規制が入ったので、以前ほど節税商品としての使いかっては良くありませんが今でもよく使われる節税商品です。
②中古車両・機械の購入節税
建設業に必須なものといえば、車両やダンプ、ホイールローダーやユンボなどの建設機械があります。
この必要な自動車や建設機械はある程度高額になります。
この車両・機械は減価償却費という経費になっていくものですから、購入時に一発経費にはならないのです。
お金は一発で払って、経費は何年にもかけてちょっとずつというのが減価償却とお金の関係です。
大きな経費が欲しくて、かつ、キャッシュと経費のバランスをよくしたいというときに選ばれやすいのが中古の設備投資です。
ここでよくいただく質問が「銀行融資を受けたほうが良いのか」というものがあります。
金額の大きなものを購入するときには資金調達とセットで進めることをお話ししています。
③事前確定届出給与による節税
事前確定届出給与は積極的に対応している税理士事務所とやりたがらない税理士事務所に分かれます。
私たちは積極的に「事前確定届出給与」は使っています。
決算終了後の株主総会から1か月以内に税務署に届出書を出すことで、役員に対してボーナスの支給ができるというものです。
利益が出なけば、支給を取りやめることもできるので経営者にとってもよいモチベーションになる節税です。

2.建設業の経営者によって節税に関する答えが違う理由
色々な経営者の方とお話をしていると「節税」に対する考え方も違えば、アドバイスとして出してくるものが違ったりします。
アドバイスの違いは経営者の視座によることが多い
建設業の経営者でも一人親方から〇〇億円という規模まで様々な規模があります。
その規模に至るまでの経験や経営者としての考え方によって見えている世界が違います。
自分の税金だけを考える場合は、経費を使って利益を圧縮することで税金を抑えたいという考え方が強くなります。
自分の税金だけを考えられるのは、現状維持ができればよいうという考え方の場合に合っている節税です。
売上1億を超えてくる建設業になると、スタッフの確保や昇給ということを考えていかなければ成長できないことを知っているので、金融機関との付き合い方に合わせて節税を組み立てるようになります。
成長資金を調達しながら節税をするわけですが、基本は利益を出して納税もしていくので金融機関請けが良いわけです。
節税に必要な資金の調達もできるので、利益も節税額も大きなものになってきます。
現状維持を考える経営者なのか未来志向なのかで節税アドバイスが違います。

3.建設業のための節税とお金の関係をよくする方法
成長していく建設業になるためには「節税」の考え方を変えていただく必要があります。
必要以上にものを購入したり、交際費を使いすぎたりということでは会社は弱ってしまいます。
お勧めの節税は「未来投資」ができているかどうかの視点です。
①人への投資による節税(賃上げ・採用・教育)
②将来の事業を見据えた設備投資(収益力改善の設備投資)
③利益を出すことで資金調達力向上
この3つが成長する建設業にとって必要な考え方と考えています。
どうしても最初は税金が高いから経費を多く作りたくなりますが、本当に足りないのは売上と利益です。
この売上と利益を上げるために投資する経費を作ることが効果的な節税といえます。

4.まとめ
みんな「節税をやっている」という話を聞くと自分もやらなきゃと思うかもしれません。
でも、会社を創ったのは節税をするためではなく、自分やスタッフの生活をよりよくすることだと思います。
そのためにはお客様に喜んでいただける仕事を続けていくことが必須になります。
これを達成することができる魔法の節税が「未来費用」という投資型節税です。
しかも、利益も出していくので銀行融資を受けやすい体質になります。
私たちは「お客様の未来をより良いものにする」という考え方から、この未来型節税をお勧めしています。
成長したい建設業の方は今すぐご相談ください。(℡:011-858-7007)