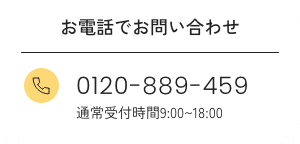「建築工事業ならでは」のお悩み解決はお任せください!
私たちは創業以来、建築工事業のお客様に支えられ、共に成長してまいりました。業務を通じてさまざまな経営者様から建築工事業ならではのリアルな現場や商習慣について教えていただきながら、貴社の経営改善に向けた取り組みを続けております。
千葉将志税理士事務所は、単なる税理士事務所としてではなく、お客様のお悩みと数字との因果関係が見えることに強みを持っています。建築工事業独自の経理処理や、現場ごとの複雑な原価管理、そして公共工事入札特有の商習慣にも精通しており、建築工事業経営のあらゆる課題解決を全面的に支援いたします。
建築工事業の方で、以下のことでお悩みではないですか?
- 見積もり段階では利益が出るはずなのに、工事が終わるとどうも手元に残らない…
- 複数の現場が同時進行する中で、それぞれの原価が複雑すぎて、赤字案件を見つけられない…
- 下請けからの見積もりも高騰し、施主への価格転嫁も難しい。利益の確保が年々厳しくなっている…
- 人材不足が深刻で、優秀な職人が集まらない。事業拡大のチャンスを逃している気がする…
- 金融機関との関係をどう築けば良いか分からない。急な資金が必要になったらどうしよう…
- 働き方改革で残業規制が厳しくなり、工期への影響や人件費の増加が心配だ…
- 会社の数字を見ても漠然としていて、次に何をすべきか具体的な経営判断ができない…
- 事業承継を考えているが、後継者が見つからず、会社をどうしたら良いか悩んでいる……
建築工事業の経営者が直面する「なぜ?」の深層

「利益と手元資金のズレ」を見誤る会計基準の罠
「見積もりでは利益が出ているはずなのに、なぜか手元にお金が残らない…」。この疑問は、建築工事業の経営者様から最も多く聞かれる声の一つです。その根源には、建設業会計特有の**「工事進行基準」や「完成基準」の理解不足があります。会計上は売上や利益が計上されていても、実際に施主からの入金がされるのは工事の進捗や完了後。資材購入や外注費の支払いは先行するため、「帳簿上の利益」と「実際のキャッシュフロー」との間に、どうしても時間差(ズレ)が生じてしまいます。**このズレを正確に予測し、資金繰り計画に落とし込めていないことが、突然の資金ショートや、事業拡大の足かせとなる大きな要因なのです。

複雑な「現場別原価管理」がもたらす採算の不明瞭さ
複数の建築現場が同時進行する中で、「どの現場が本当に儲かっているのか?」を明確に把握できていますか? 建築工事業の原価は、材料費、労務費、外注費、重機損料など多岐にわたり、一つとして同じ現場はありません。この複雑な原価を現場ごとにリアルタイムで、かつ正確に集計・分析できていないと、気づかないうちに赤字案件が紛れ込み、会社全体の利益を蝕んでいることがあります。「どんぶり勘定」になりがちな管理体制では、本来得られたはずの利益を逃し、適切な価格交渉も、効果的なコスト削減も不可能になってしまうのです。

「人手不足」と「働き方改革」が突きつける経営の壁
建設業界全体、特に建築工事業で深刻化する慢性的な人手不足は、事業規模拡大の最大の障壁です。優秀な職人が集まらない、若手人材が定着しないという問題は、単に求人広告を出しても解決しません。さらに、2024年4月1日から適用された**「働き方改革関連法による残業規制」**は、現場の稼働時間に直接影響し、工期の延長や人件費の増加といった新たな課題を突きつけています。これらの変化に対応した、給与体系の見直し、福利厚生の充実、効率的な人員配置、そして数字に基づいた採用戦略を立てられていないことが、経営者の大きな負担となっています。

経営の「羅針盤」たる数字を読み解けない情報格差
毎月届く試算表や、年に一度の決算書。「税務申告のため」と割り切って、その内容を深く読み解けていますか? 多くの建築工事業の経営者様は、現場のプロフェッショナルでありながら、自社の数字が示す「真のメッセージ」を読み解き、経営判断に活かす術を知らないために、大きな機会損失をしていることがあります。金融機関との融資交渉、新たな設備投資の判断、あるいは事業承継といった重要な局面で、数字を根拠に語れないことは、会社の成長を鈍化させるだけでなく、不要なリスクを招きかねません。数字を理解し、活用できるかどうかが、現代の建築工事業経営における決定的な情報格差となっているのです。


建設業経営の特徴
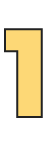
売上変動の波と安定した受注戦略の必要性
建築工事業の売上は、大型案件の受注状況や景気、さらには季節によって大きく変動します。特に、内装工事やリフォームなどは比較的安定している一方で、新築戸建てや大規模な商業施設、公共施設の建築案件は、工期が長く、一つ一つの規模が大きいため、受注のタイミング次第で年間の売上が大きく上下します。
不安定な売上による資金繰りへの影響: 大型案件が重なれば一時的に売上が伸びるものの、次の案件が決まらなければすぐに落ち込む不安がつきまといます。また、工事着手金や中間金、最終入金といった独特の支払いサイクルは、手元の資金繰りを複雑にし、「帳簿上は利益が出ているのに、なぜかお金がない」という状況を生み出しがちです。安定した経営のためには、新規顧客の開拓と、信頼関係に基づいた既存顧客からの継続的なリピート受注、そしてご紹介による仕事の獲得が不可欠です。

人材確保と厳しさを増す労務管理が経営の生命線
建築現場は「人」が全ての要です。しかし、この「人」に関する課題が、建築工事業の成長を阻む最大の壁となっています。
- ベテラン職人の高齢化と若手の育成・定着: 長年培われた技術やノウハウを持つベテラン職人の引退が進む一方で、建設業全体のイメージや労働環境から、若手の人材確保が極めて困難になっています。技術の継承が進まなければ、会社の競争力は低下し、事業規模の拡大も望めません。特に、従業員が5名や10名を超えたあたりで、社会保険への加入、就業規則の整備、適切な勤怠管理など、労務管理の壁に直面し、「組織として拡大する難しさ」を感じる経営者様も少なくありません。
- 働き方改革と労務リスクの増大: 2024年4月からの働き方改革関連法による残業規制適用は、建築工事業にとって大きな転換点です。現場作業に伴う長時間労働や休日出勤が常態化していた企業ほど、人件費の増加、工期への影響、さらには労働基準監督署からの指摘といった労務リスクが高まります。適切な労働環境の整備は、単なる法令遵守に留まらず、優秀な人材の定着や、企業のブランドイメージ向上にも直結する、経営の最重要課題です。

「見えない原価」と「不透明な利益」からの脱却
建築工事業の利益管理は、その複雑さゆえに多くの経営者が頭を悩ませるポイントです。
効果的な設備投資とキャッシュフローの最適化: 業務効率を向上させるための新しいCADシステム、大型の機材、社用車の導入は、建築工事業の競争力を高める上で不可欠です。しかし、これらの高額な設備投資は、会社のキャッシュフローに大きな影響を与えます。現金での一括購入が良いのか、銀行からの借り入れが良いのか、それともリース契約が最適なのか。それぞれの選択肢が、税金や資金繰り、そして会社の財務状況にどう影響するかを理解せずに判断することは、将来の経営リスクを高めてしまいます。
工事ごとの原価計算の精度と適正見積もり: 注文住宅、リフォーム、商業施設など、案件ごとに異なる資材費、労務費、外注費、現場管理費といったコストを正確に把握できていますか? 見積もり段階で原価を厳密に計算できていなければ、受注した時点ですでに利益が圧迫されている、あるいは赤字になっていることすらあります。工事が進むにつれてコストが膨らみ、「気づいたら利益が出ていない」という状況は、建築工事業では珍しくありません。精緻な原価管理が、適正な利益確保の第一歩です。

法令遵守、組織成長、そして事業承継の多角的課題
事業を継続し、成長させていくためには、税務や労務だけでなく、建築業に特有の法令や、組織全体の将来を見据えた計画が必要です。
規模拡大に伴う組織化と後継者問題: 従業員数や売上高が増加し、事業規模が拡大するにつれて、現場任せの管理では立ち行かなくなります。管理職の育成、現場監督と営業担当の役割分担の明確化、そして業務フローの標準化といった「組織再編」が求められます。さらに、経営者の皆様が直面するのが「事業承継」という大きな課題です。後継者が見つからない、あるいは相続税対策を含めた円滑な事業承継計画を立てられていないために、長年築き上げた会社をどうしたら良いか悩むケースが後を絶ちません。早期からの計画と、税務・法務・財務の専門知識に基づいた準備が、次の世代への確実なバトンタッチを可能にします。
建設業許可と厳格化する法的遵守: 事業を合法的に継続していくためには、建設業許可の取得と更新が不可欠です。しかし、その要件や手続きは非常に複雑であり、不備があれば行政指導や営業停止といった重大なリスクにつながります。また、労働安全衛生法、建築基準法、廃棄物処理法など、現場作業には幅広い法令が関わり、違反は企業イメージの失墜や罰則のリスクを招きます。常に最新の法改正情報をキャッチアップし、適切に対応できる体制を整えることが、経営の安定には欠かせません。

成長に伴う組織づくりと事業承継の「見えない壁」
建築工事業が順調に成長し、社員数や売上が増えてくると、新たな「壁」にぶつかる経営者の方は少なくありません。それは、これまでのやり方では立ち行かなくなる組織の課題と、避けては通れない事業承継の課題です。
「誰に託すか?」事業承継という時間との闘い: 多くの建築工事業の社長様が、長年かけて築き上げてきた会社を「誰に、いつ、どうやって託すか」という大きな悩みを抱えています。お子様が別の道に進まれたり、社内に適任者がいなかったりするケースは珍しくありません。事業承継は、後継者の育成だけでなく、自社株の評価、相続税対策、さらにはM&A(合併・買収)といった多様な選択肢を、税務や法務の専門知識に基づいて、何年も前から計画的に準備を進める必要があります。これを「まだ先の話」と先延ばしにしてしまうと、いざという時に選択肢が狭まり、最悪の場合、廃業という道を選ばざるを得なくなることも。円滑なバトンタッチのためには、早期の準備と、専門家との連携が不可欠なのです。
規模拡大で見えてくる組織のひずみ: 社員数が数名のうちは、社長が全ての現場を把握し、細部まで指示を出すことができたかもしれません。しかし、会社が成長し、社員数が増え、複数の現場が同時進行するようになると、いつまでも社長一人で全てを管理することは不可能になります。管理職候補の育成が手つかずだったり、現場監督と営業、経理といった役割分担が曖昧なままだったりすると、業務効率は低下し、情報共有も滞りがちです。結果として、せっかくの成長のチャンスを活かせず、かえって混乱を招いてしまうケースが少なくありません。これは、「属人化」からの脱却と「組織化」への移行という、経営ステージの変化に対応できていない証拠です。
建築工事業の成長を加速させる5つの経営戦略
1. 「なぜかお金がない」を解消する綿密な資金繰り計画
①日々の現金管理を徹底する重要性
出張や複数の現場で班が分かれる建築工事業では、現金の管理が複雑になりがちです。しかし、会社の現金管理がずさんになると、気づかないうちに社長への貸付金が増え、これは社長個人の税務上のデメリットになるだけでなく、金融機関からの評価を著しく下げ、将来の資金調達のハードルを上げてしまいます。私たちは、御社の状況に合わせた無理のない現金管理の仕組みづくりからご相談に乗ります。
②大きなお金の流れを「見える化」し、コントロールする
建築工事業では、売上が手形(でんさい)で入ってきたり、工事の締め日と支払いのタイミングが大きくずれたりすることが頻繁に起こります。このような入出金の時期のずれを「サイト」と呼びますが、売上が大きくなり会社が成長する時期には、このサイトのずれによって、見かけ上の利益以上に「お金」がどんどん必要になるケースが多々あります。また、高額な建設機械や車両、CADシステムなどの設備投資の際にも、まとまった資金が必要です。私たちは、定期的に綿密な資金計画を立て、金融機関から最適な形で資金調達を行うお手伝いをいたします。日頃から金融機関からの評価が高い「魅せる決算書」を作成することも、資金調達をスムーズにする重要なポイントです。
2. 受注戦略の最適化:顧客層に応じたアプローチ
①元請けからの受注:時期と「与信」を見極める
同業者である元請けからの受注は、安定した仕事量をもたらす一方で、時期と相手先の「与信」を見極めることが非常に重要です。仕事が薄い時期に無理に新規開拓を進めると、その後の受注金額も低く抑えられてしまうことがあります。人材確保に余裕があるうちに、仕事がある時期にこそ新規開拓を行う方が、価格面で優位性を保ちやすくなります。ただし、新規開拓の際には、相手の支払い能力を事前に確認する「与信管理」を怠ると、入金トラブルに巻き込まれるリスクが高まるため注意が必要です。
②一般のお客様からの直接受注:マーケティングの力で差別化を図る
解体業、塗装業、外構工事業、管工事など、建築工事業の特定の業種では、一般のお客様からの直接受注が大きな柱となり得ます。こうしたお客様を集めるためには、マーケティングの知識が不可欠です。単に広告を出すだけでなく、ターゲット層に響くキャンペーンの企画、SNSを活用した情報発信、自社の強みを伝えるウェブサイト構築など、集客のための戦略的なアプローチが成功の鍵を握ります。
③「リピート受注」を見込める仕組みづくりで安定経営へ
一度工事を完了したお客様との関係性をいかに継続させるかが、中長期的な売上安定の要となります。完工後の定期的なフォローアップ、アフターメンテナンスの充実、お客様の声の収集などを通じて、高い顧客満足度を維持する仕組みを構築しましょう。お客様からの信頼は、次の再依頼だけでなく、新たな顧客の紹介にも繋がり、安定した経営基盤を築く上で最も効果的な戦略となります。
3. 組織体制と人材マネジメント:未来を担う「人」への投資
「選ばれる会社」になるための採用と定着率アップ
学校や訓練校への積極的な求人活動に加え、SNSや自社の採用サイトを魅力的に構築することが、若手人材の獲得には不可欠です。若い世代の採用を目指すなら、単に給与を上げるだけでなく、昇給し続けられるだけの「利益体質」の会社にすること、そして福利厚生の充実や労働環境の整備が非常に重要になります。今後5年、10年先を見据えた時、若い人材を継続的に採用・定着させられる会社こそが、市場で「選ばれる建設業」として成長していく可能性を秘めているのです。
適材適所の配置と人間関係を含めた人材育成
建築工事業での離職理由として非常に多いのが「現場の人間関係」です。これは、単なる技術力の問題だけでなく、チームワークやコミュニケーション能力が求められる現場特有の課題と言えます。若手に技術力を確実に伝えていくためには、単に建設業の技術指導だけでなく、人間関係の構築やコミュニケーションスキルに関する教育も必要不可欠です。その上で、社員一人ひとりの強みや適性を見極め、最適な現場への配置を行う「適材適所」のマネジメントが、組織全体のパフォーマンスを最大化し、強いチームを作り上げる鍵となります。
4. 利益率を意識した原価管理と実務的経営分析
毎月経理による「見えない赤字」の早期発見
建築工事業でよくありがちなのが、「経理はまとめて決算前にドン」というやり方です。これでは、どの現場が儲かったのか、あるいは赤字だったのかが、手遅れになってからしか分かりません。毎月きちんと経理を行うことで、たとえ複雑な現場管理が難しい規模であっても、会社経営に必要な利益の状況をリアルタイムで把握できます。専門の事務員さんがいる会社では、原価管理ソフトを導入し、現場ごとの予算と実績を細かくチェックすることで、迅速な意思決定が可能になり、不必要な赤字の拡大を防ぐことができます。
「脱どんぶり勘定」で実現する実務的経営分析
「なんとなくの肌感経営」は、時に現状と近い数字を示すこともありますが、経営を積極的に良くしていく「改善」には不向きです。どうせ決算に向けて経理をしなければならないのですから、その経理作業を「経営を良くするためのツール」として活用しましょう。そこで作られた数字を、難解な専門用語を使わず、「経営的に意味のある数字」へと変換します。 「どうしたらもっと利益が出せるのか?」「どうすれば適切な値上げができるのか?」「どうすれば優秀な人材を採用できる環境にお金を使えるのか?」—これらは、決して難しい経営分析から導き出されるものではありません。建築工事業の実務的な側面を深く理解した上での経営分析から導き出せますので、ご安心ください。
5. 専門家との連携と「生きた情報」の活用
「建設業に強い」税理士・社労士との協力体制
税理士や社労士と一言で言っても、全ての士業が建設業の専門知識を持っているわけではありません。本当に「建設業に強い」税理士・社労士とは、単に帳簿をつけたり、助成金申請をしたりするだけでなく、「建設業の成功事例と失敗事例」に圧倒的に詳しいパートナーを指します。それは、数多くの建築工事業の経営者様と、具体的な経営課題について深く膝を突き合わせ、実践的な打ち合わせを重ねてきた「場数」と経験の証です。こうした、御社の悩みを本当の意味で理解し、共に解決策を探してくれるパートナーを選ぶことが、未来を左右します。
業界動向の把握と柔軟な経営方針の策定
建築工事業は、法改正や社会情勢の変化に常に先行して対応が求められる業界です。例えば、法人への社会保険加入の徹底も、建設業では他の業種に先駆けて強化されてきました。特定の元請けや数社からの受注に依存していると、業界全体の単価相場や新しい工法、他社の成功事例といった「生きた情報」が入りにくくなります。また、若い人材の採用に力を入れている企業であれば、建設業界内だけでなく、他の業種との人材獲得競争も意識した経営方針を柔軟に策定していくことが、今後の成長において非常に重要な視点となります。
当事務所が建設会社のお客様から喜ばれている4つの理由

1、建設業の顧問先累計100社以上の実績
私たちは創業以来、建設業のお客様に支えられ、成長してきました。税理士として多くの建設業経営者と関わる中で、業界特有の悩みや特徴を深く学んできました。
私たちの強みは、お客様の悩みと数字の因果関係を把握できることです。業況が良い会社とそうでない会社の違いは、経営者の考え方や行動習慣、数字の構造にあります。成功にはさまざまなパターンがありますが、失敗には共通するシンプルなパターンが存在します。
建設業を長年見続けてきた経験を活かし、成功の可能性を高める具体的な提案ができることが私たちの強みです。

2、建設業特有の資金繰り問題に対応できる
建設業では、資金繰りや財務が大きな課題となりがちです。売上至上主義で成長を続けると、財務状況が悪化し、長期的な成長が難しくなることがあります。
私たちは、業界特有の取引慣行や、会社ごとの成長段階に合わせた資金調達を提案できます。また、建設業内でも業種ごとに売上構造が異なるため、それに応じた売上改善の方法をアドバイスします。こうした業種や会社の特徴に合わせた支援が、建設業のお客様に選ばれる理由のひとつです。

3、経営全般について相談できる
建設業には、複雑な経理や資金繰り、人材不足、仕事の取り方など、特有の課題が多くあります。私たちは、こうしたお金に関わる問題だけでなく、業界特有の経営課題にも対応し、具体的なアドバイスを行っています。 多くの会計事務所が節税を強調しますが、私たちは会社の利益とキャッシュを増やす経営を提案します。残るお金を増やせれば、無理な節税で資金を減らす必要はありません。
税金やお金の問題への対応だけでなく、経営計画を通じて建設業の長期的な経営改善にも取り組んでいます。

4、会社の将来の収益力を上げる
「社員が売上アップに貢献してくれない」と悩む会社は少なくありません。しかし、幹部や後継者、社員が「なぜ売上を上げる必要があるのか」を理解すれば、大きな戦力になると思いませんか? 最近注目されているリファラル採用では、社員が知人を紹介して採用につなげます。採用や定着が難しい建設業では、この仕組みを活用するためにも社員教育が重要です。
私たちは、幹部・後継者・社員が売上アップや生産性向上に意欲を持てるようになる社内勉強会を実施しています。
建設業経営者の方からのよくあるご質問・ご相談の例
採用に苦労しています。よい方法はないでしょうか?手元の預金で払える状況で建設機械を導入しようと思いますが、リースか融資での購入か、どちらがよいでしょうか?
建設業にとって、建設機械や各種車両は事業を行うために重要です。こうした機械やダンプ等の車両の購入を検討する機会は、非常に多くあります。特に、現預金が1,000万円ほどある状況で、機械・車両の導入を検討しているというご相談をよくいただきます。
建設業は資金の増減が大きな業種ですので、資金繰りの面から短期および中期の資金予測をしたうえで、一括払いをしても大丈夫かどうかを考えていきましょう。特に人の採用を考えなければならない場合は、慎重に考えた方がよいでしょう。
リースの場合の経営リスクとして、支払いが遅れると機械・車両を引き上げられてしまい事業継続が難しくなることが挙げられます。そのため、融資が得られるのであれば、銀行融資を利用しての購入をおすすめします。私たちは、このような設備資金の融資のご紹介もしておりますので、ご安心ください。
銀行の方から「融資を受けませんか?」と言われたのですが借りた方がよいでしょうか?
自分から融資を受けたいというだけではなく、金融機関から「融資を受けませんか?」と営業に来られることもあります。
私がまだ経験の浅い頃、このようなご相談をお客様からいただいた際には「借りてほしいと言っているなら、借りた方がよいと思います」と伝えてしまっておりました。しかし、本当に借りた方がよいかどうかは、会社の状況やこれからの計画によって違ってきます。
何も考えず、低金利でお得だからととりあえず少額の融資を受けてしまうと、いずれ本当に必要な金額を借りたい場合に満額での融資が受けられないことがあります。会社の置かれている状況によっては、融資を受けると将来的にデメリットがある場合もありますので、ぜひ一度ご相談ください。
建設業で売上を増やしたいのですが、どうしたらよいでしょうか?
同じ建設業でも、業種によって売上の増やし方は変わってきます。
一例として、人工受けで仕事をしている場合は、単純に現場に入ってもらう従業員の数を増やすことが重要となります。つまり、採用ができなければ売上を増やすのは難しいということになります。売上が伸びず、採用資金が足りなくなるという悪いサイクルに入らないようにしていきましょう。
私たちは、このような悪循環に陥ることのないよう、元請け先の選び方・単価交渉・見積もりの出し方・採用方針についてのミーティングをお客様と行っています。実際に、見積もりの出し方を変えただけで売上・利益ともに増加し、大変喜んでいただけた事例もございます。
建設業で仕事の少ない時期があって困った経験があります。そのような場合はどうしたらよいのでしょうか?
建設業の業種にもよりますが、冬季に仕事の薄くなりやすい業種や、新築工事・リフォーム工事など景気に左右されやすい業種などがあります。仕事が忙しい時期と、仕事があまりない時期とで対策が変わってきます。
私たちには建設業のお客様が多いため、同じ時期でも忙しい会社様と、仕事が薄いお客様がいらっしゃることがあります。その場合には、仕事があまりなくて困っているお客様に対し、今忙しくて大変というお客様をご紹介することもしております。
お客様同士のマッチングとなりますので、素性のわからない初めての取引先に対する不安もなく、安心して話ができると喜んでいただいております。
また、仕事の少ない時期にいつも困ってしまう場合は、経営的な視点から問題が見つかる可能性もあります。その場合は、事業構造の改善と、採用・資金手当を併せて行っていきます。
建設業の許可を取った方がよいでしょうか?許可の手続きもお願いできますか
建設業許可が必要な業種であれば、許可取得をおすすめしています。
私たちは、建設業のお客様の売上を大きく伸ばし、利益も増やしていく対策をとっていきます。そのためには、受注単価を上げていくことが必要です。
建設業許可がなければ、1現場あたり500万円未満の工事しか受注できないため、成長速度が遅くなってしまいます。建設業許可を取得することで、営業力の強化と収益力向上を図っていきましょう。
建設業の許可手続きについては、建設業に強い行政書士をご紹介しておりますのでご安心ください。
ご依頼の流れ

無料相談のお申し込み
お電話もしくはメールフォームにて、お申し込みください。申し込み後、当事務所の担当者よりご希望日をお伺いし、日程調整をさせていただきます。お電話の場合は、お電話口で日程調整をいたします。
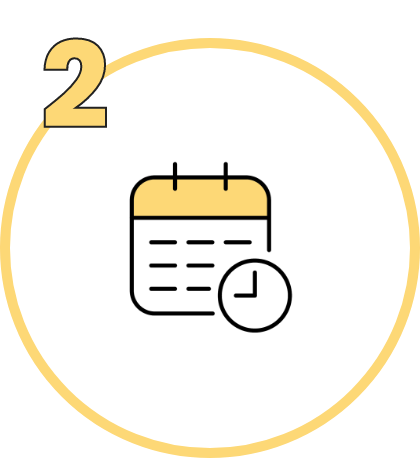
無料相談の日程確定
面談はご来社いただくか、ご希望により出張相談も承ります。お客様のご都合により、ご自宅・お仕事先からの「オンライン面談(Zoom)」にも対応しております。お気軽にお申し出ください。

無料相談の実施
ご相談時間は90分なので、たっぷりとお話いただけます。必ず税理士有資格者が対応し、丁寧にわかりやすくお話しさせていただきます。
その他よくあるご質問
-
顧問料はどのような基準で決まりますか?当社の規模に見合った料金設定なのか不安です。
-
提供するサービスとお客様の売上の組合せによって変わります。私たちはお客様の将来の不安を解消できるように、会社の数字の意味をしっかりお伝えし、目標を数字によって設定していくお手伝いをしていきます。つまり、会社が目指したい状況を数字で管理・チェックしていくというサービスですのでお客様の売上・利益を増やすことで報酬料金が上がっていく仕組みとなっております。
-
月次で具体的にどのようなサポートをしていただけるのでしょうか?単なる記帳代行以上の価値を得られるか確認したいです。
-
通常の記帳代行で得られるものは過去の数字です。私たちとのミーティングは明日からどうやって売上・利益をさらに増やしていけるかを検討する会議の場になります。売上を増やすために単価の考え方や人の採用プランなど売上・利益を上げるために必要なものは何かなどを真剣に考える時間の確保につながります。結果として、社長が日々経営という視点でより大きな売上・利益・キャッシュを生み出せる体質に変わっていきます。
-
税務だけでなく、経営面でのアドバイスも受けられますか?人材確保や価格設定など、経営全般の相談もできるのでしょうか?
-
もちろん可能です。同じ建設業といっても収益構造が異なっているので、その会社のステージに応じた成長プロセスがございます。こういった決算申告用の見方ではわからない経営的な視点で経営相談が可能です。
経営的なアドバイスを希望されている場合には、経営型のミーティングを行っております。実績として単価アップ検討や商品検討などもさせていただいております。人材確保につきましては、人材確保予算の算定や長期ビジョンから人材採用の可否についてもミーティングも行っております。
-
将来的な事業体制展開や事業拡大を考えた場合、どのタイミングで法人化すべきか相談できますか?
-
法人化相談事例はたくさん経験しております。税務面だけでなく経営的な側面から法人化するタイミングや法人化した後の成長のお手伝いをしております。
-
スタッフの給与体系や福利厚生の設計について、税務面と人材確保の両面からアドバイスいただけますか?
-
採用に影響していくのは現社員の給与水準と昇給水準です。この給与体系や採用しやすい福利厚生の財源の作り方や具体的な相談もいただいております。
-
遠方ですが、依頼を受けていただけますか?
-
Zoomやチャット等を活用し、遠方の方にも対応しております。実際に、海外の顧問先様もいらっしゃいます。
-
緊急で相談したいことが発生した場合、どの程度迅速に対応していただけますか?
-
私たちの事務所は担当以外も含め全社的にサポートをするようになっています。最短の場合は数分、遅くとも24時間以内には対応を開始しております。
-
顧問契約を結んだ後、相性が合わないと感じた場合の契約解除条件はどうなっていますか?
-
税理士事務所との相性は非常に重要です。相性が合わない場合は契約解除を即時でできるプランと、更新月で解除する2つのプランをご用意しておりますので、不安な場合は即時契約解除可能プランを選択ください。
-
現在、顧問税理士がいるのですが、相談してもよいでしょうか?税理士を変える時に、既存税理士に高圧的に言われそうで怖いのですが…。
-
もちろんです。事情があって顧問税理士を変えられない場合でも、当事務所を経営専門のセカンドオピニオンとして活用いただくことも可能です。お気軽にご相談ください。
既存の税理士顧問を変えたい場合、引き継ぎマニュアルをお渡しいたします。
-
経理や税金以外の相談はできますか?
-
経理・税務はもちろんのこと、経営全般について幅広く対応しております。むしろご相談が多いのは経営そのものです。売上アップ・人材・財務など会社の経営上の悩みの相談を多くいただいております。
-
定期的にお話しできる機会はありますか?
-
面談は年1、2回という一般的な税理士事務所とは異なり、当事務所では定期的な面談の機会を設けております(対面・オンライン)。定期的に顔を合わせて話すことでお互いの理解が深まり、相談しやすい関係をつくることができると考えています。
-
料金が高いと感じるのですが…
-
一般的な税理士事務所の税務顧問は経理チェック・確定申告をメインに行います。ただの作業料に対する価格と考えるともっとリーズナブルな事務所もございます。
ですが、私たちは「経営をよくすること」を目標とした、コンサルティング型のサービスを提供しています。お客様の経営の価値向上に貢献することを目的としているサービスですので、数字のチェックや節税アドバイスだけしてくれればいいとお考えの方には、向いていないかもしれません。