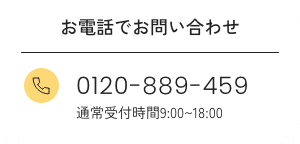「建設業ならでは」のお悩み解決はお任せください!
私たちは創業以来、建設業のお客様に支えられて成長してきました。業務を通じてさまざまな経営者様から建設業について教えていただきながら、建設業の経営改善に向けた取り組みを続けてまいりました。
私たちは税理士事務所として、お客様のお悩みと数字との因果関係が見えることに強みがあります。
建設業独自の経理や商習慣にも精通しており、建設業経営のあらゆる課題解決を支援いたします。
建設会社の方で、以下のことでお悩みではないですか?
- 人が採用できない、退職者が多い
- 従業員の給与を上げたいがどうしてよいかわからない。
- 後継者・幹部教育ができない
- 事業承継対策ができない
- 日々忙しくてどうしたら売上を伸ばせるのかわからない
- 下請けで単価交渉がうまくできない
- 公庫・銀行・信金・信組などの金融機関とのつき合い方がわからない
- 購入かリースか、どちらがよいか判断がつかない
- 建設業特有の資金繰りの相談ができない
- 税金をどれくらい払わなければならないのか、いつもわからず不安
- 建設業の経営相談の成功事例がある税理士を知らない
なぜ、このようなことが起こってしまうのか?

建設業の業種の多さ
建設業と一口にいっても、その中にさらにたくさんの業種があります。建設業の許可種目だけでも内装工事業、道路工事業など28種目がありますが、そういった事情を知らない・理解しようとしない税理士が多くいるのが現状です。
特に北海道の建設業の場合は、通年雇用安定奨励金の関係や、本州の現場に出る・出ないなど、特有のさまざまな事情を知っている必要もあります。ただ数字を見るだけでなく、業界に精通していなければ課題を解決することができません。

建設業特有の経理がある
建設業の会計は、一般企業よりも複雑な「建設簿記」という独自の会計方法で行われます。 建設業に詳しくない記帳代行会社や税理士事務所に依頼すると、建設業特有の会計基準に適合しない経理処理が行われる可能性があります。
その結果、税務調査の際に重大な誤りを指摘され、予想外の高額な税金を支払う事態になりかねません。
さらに、経理方法の違いは金融機関からの評価にも影響を与えるため、資金調達の可能性を左右することもあります。

人材不足
人口減少によりどの業界でも人材不足が課題となっていますが、建設業界では特に深刻です。労働者の高齢化が進み、「60歳はまだ若い」と言われるほど、現場では高齢者が働き続けています。
元請けゼネコンでも採用した人材が定着せず、人材不足に悩んでいます。 業界内だけでなく業種を超えた人材獲得競争が激化し、採用に成功しない会社はさらに選ばれなくなる可能性があります。一方、AIの影響を受けにくい建設現場では、人材採用が上手な会社ほど成長が期待できます。
人材確保への対策は、貴社の成長につながる大きなチャンスです。建設業の経営において人材確保は最重要課題です。

資金繰りの問題
建設業の経営者が陥りがちなミスは、金利だけで金融機関を選ぶことです。資金調達で重要なのは資金繰りであり、金利が低くても避けるべき融資や、金利が高くても会社の安全性を高める資金調達があります。
私たちは具体的な事例を交え、適切な資金調達方法を提案し、経営者や幹部の資金繰りスキル向上をサポートします。また、建設業特有の資金繰りの厳しい時期や設備投資計画に備えた金融機関との交渉も支援し、大きな資金需要にも安心して対応できる体制を整えます。


建設業経営の特徴
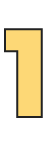
売上の変動幅が大きい
建設業は工期や案件規模によって売上が大きく上下します。特に屋外工事が多い業態では、天候の影響を受けやすいため、資金繰りを安定させる工夫が必要です。
新規顧客開拓とリピート受注の両立が課題
大きな案件が続けば一時的に売上が伸びますが、継続的に案件を獲得しないと売上が落ち込みがちです。新規開拓を進める一方で既存顧客との関係性を強化することが求められます。

人材確保・労務管理が経営のカギ
ベテランと若手のバランス確保
技術の継承が重要な一方で、若手の確保や教育が進まなければ組織は拡大しづらくなります。また、経営規模の拡大に伴って「5名の壁」を感じるケースも多いでしょう。
労務リスクへの対応
現場作業に伴う長時間労働や休日出勤、社会保険への加入漏れなど、労働環境を適切に整備することは人材定着の面でも不可欠です。

工事原価・利益管理の複雑さ
案件ごとの原価計算と適正見積もり
資材費や外注費、労務費など工事現場で発生するコストは多岐にわたります。見積もり段階で原価を正しく把握しなければ、利益が圧迫されるリスクがあります。
適切な設備投資のタイミング
新しい機材や車両の導入は業務効率の向上に直結しますが、キャッシュフローを圧迫する要因にもなります。リース・ローン・現金購入などの選択肢を検討し、負担を最小化することが大切です。

法令や許可申請への対応が必要不可欠
事業を継続するうえで欠かせない建設業許可の取得・更新は、要件や手続きが複雑です。不備があると営業停止などのリスクが高まるため、専門家と連携するケースも増えています。
-安全基準・環境規制の遵守
労働安全衛生法や廃棄物処理法など、現場作業には幅広い法令が関わります。違反は企業イメージの低下や罰則のリスクにつながるため、常に最新の情報をキャッチアップする必要があります。

成長に伴う組織づくりと事業承継課題
規模拡大時の組織再編
社員数や売上高が増えると、組織体制の再構築や管理業務の効率化が求められます。管理職候補の育成や、現場監督・営業担当の役割分担を明確にすることがカギです。
後継者問題と早期の準備
事業承継・相続税対策は経営者の年齢や企業の将来を見据えて計画的に進める必要があります。後継者の育成はもちろん、株式の評価や分割など税制面の検討を早めに行うことで、円滑なバトンタッチが可能となります。
建設業を経営していく上で重要なポイント
1. 綿密な資金繰り計画
①お金の管理をしっかりする
出張や班が分かれてお金の管理が難しい業種ですから、会社の現金管理が上手くできない業種です。お金の管理が悪くなると社長への貸付金が増えて、社長個人のデメリットと金融機関評価が悪くなることでの資金調達ハードルが上がるので現金管理の仕方もご相談ください。
②大きなお金の流れをコントロールする
建設業では売上が手形(でんさい)で入ってきたり、締め支払いのタイミングがずれることが良く起こります。このような入出金時期のずれをサイトと呼びますが、売上が大きくなって成長する時期にはサイトずれでお金がどんどん必要になってきます。また、建設機械や車両購入など設備投資の際にも大きなお金が必要になります。定期的に資金計画をたてて金融機関から上手に資金調達をしていきましょう。
日頃から金融機関からの見られ方の良い決算書の作成も重要なポイントになります。
2. 受注対象は「建設業」か「一般の方」かで異なる方法
①建設業の元請けからの受注
同業者からの受注は時期と与信が重要になります。仕事の薄い時期に新規開拓をするとその後の受注金額も低めに抑えられてしまうことがあります。人材確保をしつつ仕事のあるうちに新規開拓をする方が金額面での優位性が出ます。ただし、新規開拓の際には相手の会社の支払い能力などの与信をしないと入金トラブルが増えています。
②一般の方からの直接受注
建設業の解体業・塗装業・外構工事業・管工事など業種によっては一般の方からの直接受注が可能です。一般の方の集客にはマーケティング知識を活用してキャンペーンやSNSの活用もお勧めです。
③リピート受注を見込める仕組みづくり
完工後のフォローやアフターメンテナンスを充実させることで、紹介や再依頼につなげられます。顧客満足度が高まると、中長期的な売上の安定が期待できるでしょう。
3. 組織体制と人材マネジメント
採用活動と定着率アップ
学校や訓練校などでの求人活動、SNSや自社の求人サイトの構築も大切です。若い方の採用を目指す場合には、昇給し続けられるだけの利益体質の会社にすることと、福利厚生や労働環境を整えることも重要です。若い方の採用ができる会社が今後5年・10年後で選ばれ、成長していく建設業になる可能性があります。
適材適所の配置と人材育成
建設業の離職に多い理由は「現場の人間関係」です。若手に技術力を伝えていくためにも、社員への建設業の技術だけではない人間関係についての教育も必要です。そのうえで、組織が強くなるための適材適所の配置をしていきましょう。
4. 利益率を意識した原価管理と経営分析
毎月経理による原価把握
建設業によくありがちな「経理はまとめてドン」だと、どの現場が儲からなかったのかわからないということが起こります。毎月経理することによって、難しい現場管理ができない規模でも会社経営に必要な利益の把握ができます。専門の事務員さんの雇用ができている会社は原価管理ソフトで現場ごとの予算と実績をチェックすることもお勧めです。
脱どんぶりからの経営分析
建設業のよくあるのは「なんとなくの肌感経営」です。肌感と決算数字は近いこともあるのですが、経営を良くしていくという改善には不向きです。どうせ決算に向けて経理をしなければならないので、経営が良くなるために経理をしましょう。そして、そこで作られた数字を「経営的に意味のある数字」にしていきます。
どうしたらもっと利益が出せるのか?どうしたら値上げができるのか?どうしたら採用できる環境にお金を使えるのか?
これらは難しい経営分析ではなく建設業の実務的経営分析からできます。今までの難しい話は必要ないのでご安心ください。
5. 専門家との連携と情報収集
税理士・社労士との協力体制
税理士・社労士といっても建設業に強い税理士・社労士がいることをご存じでしょうか?建設業に強い税理士・社労士は「建設業の成功事例と失敗事例」に詳しいといえます。ただ、帳簿をつけたり助成金申請をしているのではなく、実務の中で建設業の経営者の方と経営的な打合せの場数が多い税理士・社労士が建設業に強い士業です。
こうした建設業の成功事例・失敗事例に詳しいパートナーをお勧めします。
業界動向の把握と柔軟な経営方針
常に建設業は制度の先端を走っています。法人への社会保険の加入徹底の前段階から建設業は社会保険加入強化が実施されていました。特に1社専属の建設業は情報源が限られてしまうので、他の建設業の単価などの情報は重要になります。
若い方の採用に力を入れている建設業の方は他の業種との人材獲得競争を意識した経営方針も重要になってきます。
当事務所が建設会社のお客様から喜ばれている4つの理由

1、建設業の顧問先累計100社以上の実績
私たちは創業以来、建設業のお客様に支えられ、成長してきました。税理士として多くの建設業経営者と関わる中で、業界特有の悩みや特徴を深く学んできました。
私たちの強みは、お客様の悩みと数字の因果関係を把握できることです。業況が良い会社とそうでない会社の違いは、経営者の考え方や行動習慣、数字の構造にあります。成功にはさまざまなパターンがありますが、失敗には共通するシンプルなパターンが存在します。
建設業を長年見続けてきた経験を活かし、成功の可能性を高める具体的な提案ができることが私たちの強みです。

2、建設業特有の資金繰り問題に対応できる
建設業では、資金繰りや財務が大きな課題となりがちです。売上至上主義で成長を続けると、財務状況が悪化し、長期的な成長が難しくなることがあります。
私たちは、業界特有の取引慣行や、会社ごとの成長段階に合わせた資金調達を提案できます。また、建設業内でも業種ごとに売上構造が異なるため、それに応じた売上改善の方法をアドバイスします。こうした業種や会社の特徴に合わせた支援が、建設業のお客様に選ばれる理由のひとつです。

3、経営全般について相談できる
建設業には、複雑な経理や資金繰り、人材不足、仕事の取り方など、特有の課題が多くあります。私たちは、こうしたお金に関わる問題だけでなく、業界特有の経営課題にも対応し、具体的なアドバイスを行っています。 多くの会計事務所が節税を強調しますが、私たちは会社の利益とキャッシュを増やす経営を提案します。残るお金を増やせれば、無理な節税で資金を減らす必要はありません。
税金やお金の問題への対応だけでなく、経営計画を通じて建設業の長期的な経営改善にも取り組んでいます。

4、会社の将来の収益力を上げる
「社員が売上アップに貢献してくれない」と悩む会社は少なくありません。しかし、幹部や後継者、社員が「なぜ売上を上げる必要があるのか」を理解すれば、大きな戦力になると思いませんか? 最近注目されているリファラル採用では、社員が知人を紹介して採用につなげます。採用や定着が難しい建設業では、この仕組みを活用するためにも社員教育が重要です。
私たちは、幹部・後継者・社員が売上アップや生産性向上に意欲を持てるようになる社内勉強会を実施しています。
建設業経営者の方からのよくあるご質問・ご相談の例
採用に苦労しています。よい方法はないでしょうか?手元の預金で払える状況で建設機械を導入しようと思いますが、リースか融資での購入か、どちらがよいでしょうか?
建設業にとって、建設機械や各種車両は事業を行うために重要です。こうした機械やダンプ等の車両の購入を検討する機会は、非常に多くあります。特に、現預金が1,000万円ほどある状況で、機械・車両の導入を検討しているというご相談をよくいただきます。
建設業は資金の増減が大きな業種ですので、資金繰りの面から短期および中期の資金予測をしたうえで、一括払いをしても大丈夫かどうかを考えていきましょう。特に人の採用を考えなければならない場合は、慎重に考えた方がよいでしょう。
リースの場合の経営リスクとして、支払いが遅れると機械・車両を引き上げられてしまい事業継続が難しくなることが挙げられます。そのため、融資が得られるのであれば、銀行融資を利用しての購入をおすすめします。私たちは、このような設備資金の融資のご紹介もしておりますので、ご安心ください。
銀行の方から「融資を受けませんか?」と言われたのですが借りた方がよいでしょうか?
自分から融資を受けたいというだけではなく、金融機関から「融資を受けませんか?」と営業に来られることもあります。
私がまだ経験の浅い頃、このようなご相談をお客様からいただいた際には「借りてほしいと言っているなら、借りた方がよいと思います」と伝えてしまっておりました。しかし、本当に借りた方がよいかどうかは、会社の状況やこれからの計画によって違ってきます。
何も考えず、低金利でお得だからととりあえず少額の融資を受けてしまうと、いずれ本当に必要な金額を借りたい場合に満額での融資が受けられないことがあります。会社の置かれている状況によっては、融資を受けると将来的にデメリットがある場合もありますので、ぜひ一度ご相談ください。
建設業で売上を増やしたいのですが、どうしたらよいでしょうか?
同じ建設業でも、業種によって売上の増やし方は変わってきます。
一例として、人工受けで仕事をしている場合は、単純に現場に入ってもらう従業員の数を増やすことが重要となります。つまり、採用ができなければ売上を増やすのは難しいということになります。売上が伸びず、採用資金が足りなくなるという悪いサイクルに入らないようにしていきましょう。
私たちは、このような悪循環に陥ることのないよう、元請け先の選び方・単価交渉・見積もりの出し方・採用方針についてのミーティングをお客様と行っています。実際に、見積もりの出し方を変えただけで売上・利益ともに増加し、大変喜んでいただけた事例もございます。
建設業で仕事の少ない時期があって困った経験があります。そのような場合はどうしたらよいのでしょうか?
建設業の業種にもよりますが、冬季に仕事の薄くなりやすい業種や、新築工事・リフォーム工事など景気に左右されやすい業種などがあります。仕事が忙しい時期と、仕事があまりない時期とで対策が変わってきます。
私たちには建設業のお客様が多いため、同じ時期でも忙しい会社様と、仕事が薄いお客様がいらっしゃることがあります。その場合には、仕事があまりなくて困っているお客様に対し、今忙しくて大変というお客様をご紹介することもしております。
お客様同士のマッチングとなりますので、素性のわからない初めての取引先に対する不安もなく、安心して話ができると喜んでいただいております。
また、仕事の少ない時期にいつも困ってしまう場合は、経営的な視点から問題が見つかる可能性もあります。その場合は、事業構造の改善と、採用・資金手当を併せて行っていきます。
建設業の許可を取った方がよいでしょうか?許可の手続きもお願いできますか
建設業許可が必要な業種であれば、許可取得をおすすめしています。
私たちは、建設業のお客様の売上を大きく伸ばし、利益も増やしていく対策をとっていきます。そのためには、受注単価を上げていくことが必要です。
建設業許可がなければ、1現場あたり500万円未満の工事しか受注できないため、成長速度が遅くなってしまいます。建設業許可を取得することで、営業力の強化と収益力向上を図っていきましょう。
建設業の許可手続きについては、建設業に強い行政書士をご紹介しておりますのでご安心ください。
ご依頼の流れ

無料相談のお申し込み
お電話もしくはメールフォームにて、お申し込みください。申し込み後、当事務所の担当者よりご希望日をお伺いし、日程調整をさせていただきます。お電話の場合は、お電話口で日程調整をいたします。
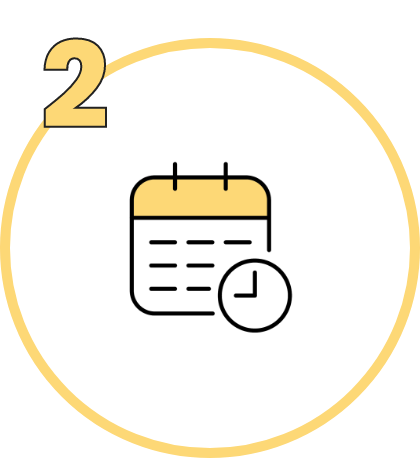
無料相談の日程確定
面談はご来社いただくか、ご希望により出張相談も承ります。お客様のご都合により、ご自宅・お仕事先からの「オンライン面談(Zoom)」にも対応しております。お気軽にお申し出ください。

無料相談の実施
ご相談時間は90分なので、たっぷりとお話いただけます。必ず税理士有資格者が対応し、丁寧にわかりやすくお話しさせていただきます。
その他よくあるご質問
-
顧問料はどのような基準で決まりますか?当社の規模に見合った料金設定なのか不安です。
-
提供するサービスとお客様の売上の組合せによって変わります。私たちはお客様の将来の不安を解消できるように、会社の数字の意味をしっかりお伝えし、目標を数字によって設定していくお手伝いをしていきます。つまり、会社が目指したい状況を数字で管理・チェックしていくというサービスですのでお客様の売上・利益を増やすことで報酬料金が上がっていく仕組みとなっております。
-
月次で具体的にどのようなサポートをしていただけるのでしょうか?単なる記帳代行以上の価値を得られるか確認したいです。
-
通常の記帳代行で得られるものは過去の数字です。私たちとのミーティングは明日からどうやって売上・利益をさらに増やしていけるかを検討する会議の場になります。売上を増やすために単価の考え方や人の採用プランなど売上・利益を上げるために必要なものは何かなどを真剣に考える時間の確保につながります。結果として、社長が日々経営という視点でより大きな売上・利益・キャッシュを生み出せる体質に変わっていきます。
-
税務だけでなく、経営面でのアドバイスも受けられますか?人材確保や価格設定など、経営全般の相談もできるのでしょうか?
-
もちろん可能です。同じ建設業といっても収益構造が異なっているので、その会社のステージに応じた成長プロセスがございます。こういった決算申告用の見方ではわからない経営的な視点で経営相談が可能です。
経営的なアドバイスを希望されている場合には、経営型のミーティングを行っております。実績として単価アップ検討や商品検討などもさせていただいております。人材確保につきましては、人材確保予算の算定や長期ビジョンから人材採用の可否についてもミーティングも行っております。
-
将来的な事業体制展開や事業拡大を考えた場合、どのタイミングで法人化すべきか相談できますか?
-
法人化相談事例はたくさん経験しております。税務面だけでなく経営的な側面から法人化するタイミングや法人化した後の成長のお手伝いをしております。
-
スタッフの給与体系や福利厚生の設計について、税務面と人材確保の両面からアドバイスいただけますか?
-
採用に影響していくのは現社員の給与水準と昇給水準です。この給与体系や採用しやすい福利厚生の財源の作り方や具体的な相談もいただいております。
-
遠方ですが、依頼を受けていただけますか?
-
Zoomやチャット等を活用し、遠方の方にも対応しております。実際に、海外の顧問先様もいらっしゃいます。
-
緊急で相談したいことが発生した場合、どの程度迅速に対応していただけますか?
-
私たちの事務所は担当以外も含め全社的にサポートをするようになっています。最短の場合は数分、遅くとも24時間以内には対応を開始しております。
-
顧問契約を結んだ後、相性が合わないと感じた場合の契約解除条件はどうなっていますか?
-
税理士事務所との相性は非常に重要です。相性が合わない場合は契約解除を即時でできるプランと、更新月で解除する2つのプランをご用意しておりますので、不安な場合は即時契約解除可能プランを選択ください。
-
現在、顧問税理士がいるのですが、相談してもよいでしょうか?税理士を変える時に、既存税理士に高圧的に言われそうで怖いのですが…。
-
もちろんです。事情があって顧問税理士を変えられない場合でも、当事務所を経営専門のセカンドオピニオンとして活用いただくことも可能です。お気軽にご相談ください。
既存の税理士顧問を変えたい場合、引き継ぎマニュアルをお渡しいたします。
-
経理や税金以外の相談はできますか?
-
経理・税務はもちろんのこと、経営全般について幅広く対応しております。むしろご相談が多いのは経営そのものです。売上アップ・人材・財務など会社の経営上の悩みの相談を多くいただいております。
-
定期的にお話しできる機会はありますか?
-
面談は年1、2回という一般的な税理士事務所とは異なり、当事務所では定期的な面談の機会を設けております(対面・オンライン)。定期的に顔を合わせて話すことでお互いの理解が深まり、相談しやすい関係をつくることができると考えています。
-
料金が高いと感じるのですが…
-
一般的な税理士事務所の税務顧問は経理チェック・確定申告をメインに行います。ただの作業料に対する価格と考えるともっとリーズナブルな事務所もございます。
ですが、私たちは「経営をよくすること」を目標とした、コンサルティング型のサービスを提供しています。お客様の経営の価値向上に貢献することを目的としているサービスですので、数字のチェックや節税アドバイスだけしてくれればいいとお考えの方には、向いていないかもしれません。