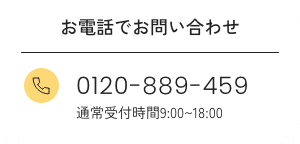【札幌の税理士が解説】高騰する人件費でも売上を持続的に伸ばす方法とは?

札幌市白石区の経営に強い千葉税理士事務所です。
「人件費が10%上がったらいくらの売上を増やさなければならないのか?」このシンプルな質問に数字で答えられますか?
昔の私は「NO」でした。
そして、当時の私のお客様もおそらく「NO」だったと思います。
あなたの会社にとって知っておいてほしい考え方をお話しします。
(目次)
1.最低賃金上昇がもたらす事態とは
2.人件費上昇に対応する3つの方法
3.社長が考える5年後を視覚化する
4.まとめ
1.最低賃金上昇がもたらす事態とは
最低賃金が2030年までに1500円になる可能性が高まっています。
単純計算では毎年100円の最低賃金アップです。
一番、影響を受けるのはパート・アルバイトの給与です。
特に飲食業の場合は最低賃金での雇用が常態化しているため、ここの求人段階で最低賃金アップの影響を受けます。
もしかすると最低賃金アップ=採用の問題だと思っているかもしれません。
しかし、本質的な問題は次のことです。
①新しい採用の最低賃金が上がる(教育最低コストアップ)
②新しいスタッフより仕事ができる人が最低賃金以下になる可能性が出る
③人件費全体をアップしないと今の時給・給与が最低賃金比較で陳腐化する
つまり、給与アップができなければ昇給してくれる他店や他業種に転職していくというリスクが高くなるという訳です。
上げる・上げないは法律的な問題だけでなく経営的な質の問題になってしまいます。
しかも、経営者のタイミングではなく待ったなしで国家ぐるみで行われることが決まっているといえます。

2.人件費上昇に対応する3つの方法
人件費上昇に対応していくためには大きく分けて3つの方法があります。
①賃上げをあきらめて人数を減らして経営する
②人数・労働時間を減らして総額人件費を維持し、賃金単価は上げていく
③人数・時間も確保したうえで生産性を上げることで対応する
個人的には②か③を選択して対策を取ることをお勧めします。
理由は①を選択した場合、経営的に弱者になる可能性が極めて高いからです。
飲食業においてよくとられる選択肢ですが、次のようなループに入っていることを認識していないケースがあります。
売上が下がる→コストカットで利益を維持→商品・サービスの質の低下→顧客満足度低下→売上ダウン・・
これを繰返していることに気が付いていないのか、気づいていてこの方法を行っているのかわからないお店が多い気がします。
一番重要なことは賃金が上がることではないのです。
一番重要なことはお客様が満足して売上・利益が増えることです。
コストカットをしても、お客様満足度が下がれば売上・利益はどんどん低下するのでデフレスパイラルに入っていきます。
どのように生産性を上げていくのかを考えていくことこそが人件費上昇局面で考えるべきことです。

3.社長が考える5年後を視覚化する
同業他社がリストラで質を下げていく中で、あなたの会社の商品・サービスの質を維持もしくは向上させたなら逆に選ばれるようになります。
生産性=付加価値÷作業時間
生産性向上は「付加価値」を増やすか、作業時間を減らすことで実現できます。
この算式を「付加価値÷人件費」で計算すると、リストラありきになるので先ほどの質の低下を招く恐れがあるので使わない方が良いと思います。
最低賃金の上昇は年間で約500円ですから、5年後までの人件費の上昇予算は計算できます。
最低賃金の上昇×離職回避×採用優位性という要素を考慮に入れた人員数・人件費を計算してみましょう。
経験者の給与を上げること・長時間すぎる労働時間を回避すること・採用求人で選ばれる給与水準という3要素を考慮に入れた人件費を作ってから、どれだけの売上・利益が必要なのかを考えていきます。
このあたりの作り方は「基礎からわかる利益計画の作り方」を参考にしていただければと思います。
利益計画を今すぐ作りたいという方は、お気軽にお電話でお問合せ下さい。(電話011-858-7007)

4.まとめ
人件費上昇は常に起こっている出来事です。
今回は今後5年で500円もの最低賃金の上昇が予測されます。
この人件費の上昇がどのような影響を与えるのかを予測し、そのためにいくらの人件費アップ予算が必要なのかをつかむ必要があります。
そのうえで粗利益をその分増やす他ことが必要になります。
数字を作り上げることにより、どのように粗利益を確保するのかを検討していくことをお勧めします。
数量限定にはなりますが「基礎からわかる利益計画の作り方」を無料でプレゼントさせていただきます。
下記公式LINEに「基礎からわかる利益計画の作り方」希望とメッセージをいただき、現在のお困りごとなどございましたら追記いただけたら嬉しいです。