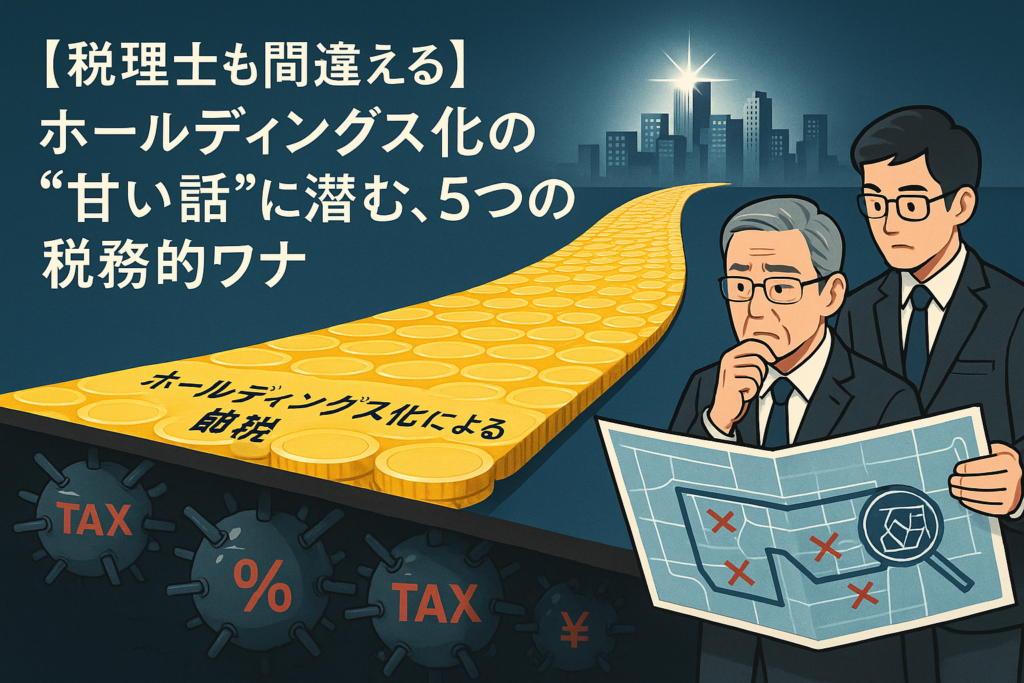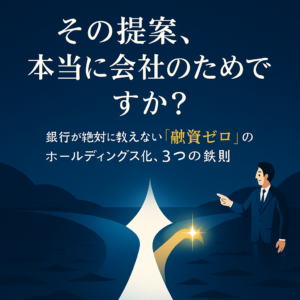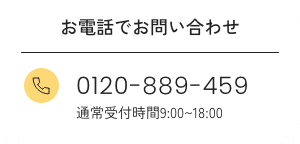★★★★★
約16分
この記事から得られる3つの効果
- ホールディングス化に潜む代表的な5つの税務リスクを、法的根拠(条文)と共に正確に理解できます。
- 税務調査で指摘されないための、具体的かつ実践的な回避策が明確になります。
- あなたの会社の組織再編が、絶対に失敗しないための「専門家による思考プロセス」を追体験できます。
ホールディングス化は、事業承継、リスク分散、成長加速など、多くのメリットをもたらす強力な経営戦略です。しかし、その強力なパワーの裏側には、**グループ法人税制**という、極めて複雑で厳格なルールが存在します。
このルールを一つでも見誤れば、節税どころか、数千万、数億円単位の追徴課税という、会社の存続を揺るがす致命的な事態を招きかねません。
本記事では、ホールディングス化を検討する全ての経営者が絶対に知っておくべき、代表的な5つの税務リスクを、**一次情報である法律の条文**を明確に示しながら徹底解説します。これは、あなたの会社の未来を守るための、法的な武装です。
1. リスク①:100%支配関係の断絶(グループ税制適用の完全喪失)
実務上のワナ
グループ法人税制の多くのメリットは、親会社と子会社・孫会社が**株式で100%繋がっている「完全支配関係」**が絶対条件です。しかし、例えば事業承継対策として、あるいは功労役員へのインセンティブとして、社長が保有する**子会社の株式を、たとえ1株でも**親族や第三者に譲渡・贈与した瞬間、この関係は崩壊します。
【法的根拠】
- 法人税法 第2条 十二の七の六:「完全支配関係」の定義。一の者が法人の発行済株式等の全部を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係をいう。
- 法人税法 第64条の9:グループ通算制度は、完全支配関係がある内国法人間でのみ適用される。
【結末】
この「たった1株」の移動により、損益通算や資産の含み損益の繰延べといった、グループ法人税制の根幹をなすメリットが全て適用不可となります。良かれと思って行った行為が、グループ全体の税務戦略を根底から覆すのです。
2. リスク②:グループ内資産移転と「時価評価課税」
実務上のワナ
「グループ内なら資産を自由に動かせる」というのも危険な誤解です。特に、含み益のある資産(土地など)を、税負担なく親会社に移してから子会社を売却しよう、といった安易な計画は、税務署から「租税回避行為」とみなされるリスクと隣り合わせです。
【法的根拠】
- 法人税法 第61条の13:完全支配関係があるグループ内の資産移転は、一定の要件下で譲渡損益を繰り延べる(=帳簿価額で移転できる)ことを規定。しかし、これはあくまで継続保有が前提。
- 法人税法 第132条の2:同族会社の行為計算の包括的否認規定。不当に法人税の負担を減少させる結果となると認められる場合、税務署長はその行為を否認し、時価で再計算できる。
【結末】
税務調査で租税回避と認定されれば、資産移転は**時価**で行われたものとされ、多額の含み益に対して法人税が追徴課税されます。節税どころか、予期せぬ巨額の納税が発生する最悪のシナリオです。
3. リスク③:グループ内取引と「寄附金認定」
実務上のワナ
「身内なのだから」という感覚で、グループ会社間で無利息の融資や、無償でのサービス提供を行うと、税務上は「寄附」とみなされ、かえって税負担が増えることがあります。
【法的根拠】
- 法人税法 第37条 第2項:完全支配関係がある法人への寄附金は、**全額が損金不算入**(経費として認められない)となる。
- 法人税法 第37条 第7項:寄附金の定義。資産の譲渡や役務の提供を、無償または低い対価で行うことを含む。
【結末】
例えば、親会社が子会社に無利息で1億円を貸した場合。親会社は、本来得られたはずの利息分を子会社に「寄附」したとみなされ、その金額は経費になりません。一方で、子会社側は利息相当額を「受贈益」として利益計上し、課税対象となる可能性があります。経済合理性のない取引は、グループ全体で税金を余計に払う結果を招きます。
4. リスク④:グループ通算制度の「5年縛り」
実務上のワナ
グループ通算制度(損益通算)は、一度適用を開始すると、その適用をやめる判断は極めて慎重に行う必要があります。安易な離脱は、将来の選択肢を失うことにつながります。
【法的根拠】
- 法人税法 第64条の9 第1項 第三号:通算承認の効力を失った日から同日以後5年を経過する日までの間に終了する事業年度においては、再度の適用は受けられない。通称**「5年縛り」**。
【結末】
ある年の赤字を利用するために制度を適用し、翌年に黒字化したからと安易に離脱。しかし、その2年後に再び大きな赤字が発生しても、5年縛りのため損益通算ができず、多額の税金を支払うしかありません。短期的な視点での制度利用は、長期的な利益を損なう危険な罠です。
5. リスク⑤:自己株式取得と「みなし配当」課税
実務上のワナ
グループ内の資本整理や、創業者利益の確定のために行われる「自己株式の取得」は、税務上の定義を理解せずに行うと、想定外の課税を招きます。
【法的根拠】
- 法人税法 第24条 第1項:自己株式の取得など、資本の払戻しとみなされる取引において、資本金等を超える部分の金額を「みなし配当」として扱うことを規定。
- 法人税法 第23条:受取配当等の益金不算入。完全子法人からの配当は全額益金不算入だが、関係性によっては課税対象となる。
【結末】
子会社が親会社から自社株式を買い戻す際、その対価は単純な「株式の売却代金」とはなりません。税法上は、一部が「資本の払戻し」、そしてそれを超える部分が「利益の分配(=みなし配当)」と見なされます。この「みなし配当」は、通常の株式譲渡益とは異なる課税ルールが適用され、特に完全支配関係が崩れている場合などには、予期せぬ法人税が課されるリスクがあります。
その組織再編、"地雷"を踏んでいませんか?
ホールディングス化は、あなたの会社の未来を左右する、極めて重要な経営判断です。
実行ボタンを押す前に、その設計図に税務上の欠陥がないか、第三者の専門家による厳格なチェックを受けるべきです。
011-858-7007
(受付時間:平日 9:00〜18:00)
「検討中のプランに、リスクがないかだけ見てほしい」というご相談を心より歓迎いたします。
投稿者プロフィール

-
中小企業社長専門の経営コンサルタント兼税理士。
1977年生まれ、札幌出身。大手税理士事務所在籍中、税理士試験に合格。「試算表を作るだけ」の業務が中心で、経営支援に踏み込めない現状に強いジレンマを抱える。大手事務所を退所し、コンサル型の税理士事務所に入所するも思い描く支援とのギャップに苦悩。28歳の頃にお客さんゼロ・計画なしという状態で独立を決意。自分自身が事務所経営に苦しんだ経験から「経営者は孤独で、悩んでも税理士に相談しにくい」という現実を身をもって痛感。ふとしたきっかけで参加した勉強会で「税理士=税金や会計処理だけではない。経営戦略まで踏み込んでサポートできる存在でありたい」という想いを強くする。様々な経験を経て、現在は北海道札幌市白石区で「建設業や動物病院をはじめ、多業種の経営者を「数字」と「現場」の両面で支えている。単価・売上・利益向上と財務、人事・採用マーケティングのサポートを得意とする経営コンサルタント。
最新の投稿
 代表コラム2026年2月4日札幌市白石区の建設業特化税理士|2026年取適法対応と利益最大化経営計画
代表コラム2026年2月4日札幌市白石区の建設業特化税理士|2026年取適法対応と利益最大化経営計画 社長の意思決定ノート2026年1月30日幹部に任せる決断が怖い社長へ|判断軸は1つ
社長の意思決定ノート2026年1月30日幹部に任せる決断が怖い社長へ|判断軸は1つ お知らせ2026年1月24日2026年の外注再定義|安易に「切る」な、外注先に「AI以上の質」を要求せよ
お知らせ2026年1月24日2026年の外注再定義|安易に「切る」な、外注先に「AI以上の質」を要求せよ AI時代の経営者向けコラム2026年1月15日退屈」を愛せ。AIには耐えられない、その単調な時間こそが「偉業」を育てる。
AI時代の経営者向けコラム2026年1月15日退屈」を愛せ。AIには耐えられない、その単調な時間こそが「偉業」を育てる。